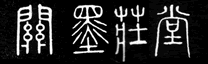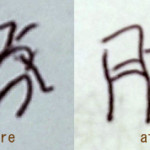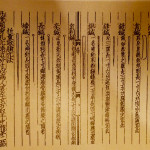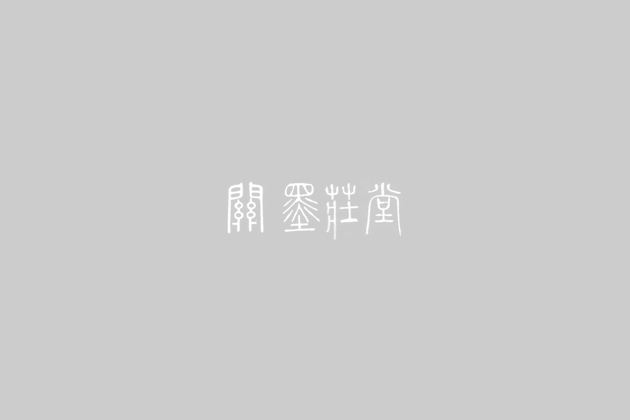墨荘堂ブログ
副鼻腔炎の鍼灸治療
もともとハウスダストと思われるアレルギーがあって鼻水が出るようになり、好酸菌性副鼻腔炎と診断された方の治療です。8年前に耳鼻科で手術をしましたが、最近また黄色の膿が溜まるようになってきて、匂いも感じられないという状況でした。
耳鼻科ではまた手術を勧められたらしいですが、蓄膿症や副鼻腔炎の手術は、原因を除いている訳ではないので、再手術ということが良くあります。手術もやった後は楽になりますが、何度も繰り返せば体に対するダメージも皆無であるとは言えません。その点鍼灸は傷などのダメージはほとんど有りませんし、甚だしい骨格の異常などが無ければ、完治も可能です。
この方も他の蓄膿症や後鼻漏と同じような治療で、主なものは頬部の細絡刺絡ですが、全身のシステムの調整や董氏奇穴も行っております。
やはり初回はかなり瘀血が出たので、2回目に様子をお尋ねしたところ、治療後に黒い膿(本人談、恐らくは濃度の高い膿)が出て、鼻の周囲の重さが取れ、匂いも感じるようになりましたとのこと。
現在4診目ですが、膿も薄れてきて、すっきりし、鼻水も減少したということでした。まだ治療途中ですが、蓄膿症や副鼻腔炎は患者さんの実感がかなり変化するので、報告することにしました。
鍼灸による姙娠管理と逆子の灸
逆子の灸は色々なところに取り上げられていて有名ですが、以前に産婦人科に勤務していた時のことを書いておきます。
逆子の灸は足の小指にある至陰というツボにするのですが、8ヶ月くらいの患者さんに医師に超音波で確認してもらいながら灸をやってみたことがあります。その時は灸をしたその場で回旋していました。
通常、臍帯巻絡(さいたいけんらく)といって、へその緒が巻きついている赤ちゃん以外はすぐに回旋することが多いようです。10人以上やりましたが、4~5回以内の治療で回旋する人が多かったように記憶しています。
また、妊娠中も安産のために三陰交というツボにお灸をすえる方法もお勧めです。この方法は『女性の一生と漢方』という名著に書かれていて、胎盤が安定する5ヶ月くらいから始めて出産まで徐々に増やしていきます。この本の著者の石野先生は「30年もやっているが一度も副作用と思えるものを見たことがない」とか「母体のためだけでなく、生まれてくる子供にも著しい効果が見られる」と書かれています。この方法で4~5人の妊婦さんを管理してみたことがあるのですが、皆、安産だった記憶があります。
最近では体外受精により根本的に妊娠継続の準備ができていない人が受精という関門を越えてしまうので、周産期になって脳梗塞や高血圧など、薬を通常のように使えないケースが増えていますが、そのような方にも刺絡や鍼灸により、胎児にも安全な治療法が数多くあります。もちろん難しいケースの方は安定期に入ってからすぐ始めた方が効果がありますし、安産につながります。
近年、産婦人科が激減して助産師さんで出産される方が増えているようですが、そう言う方向をめざしている自己管理のできる方には、ぜひ試していただきたいです。
その他不妊や妊娠中の症状に関してはこちら
鍼灸で顔面神経麻痺を短期間に治すには
顔面神経麻痺はヘルペスウィルスの感染が原因のハント症候群によるものがあり、西洋医学では難聴や顔面麻痺は後遺症として残るケースもあるため、早期の治療が望ましいとして抗ウイルス薬、ステロイド薬の服用や点滴注射を行うことがあります。
この患者さんは、某都内大手私立病院でハント症候群の顔面神経麻痺と診断され、入院してステロイドの治療をしましょうと言われたのですが、ステロイドはあまり使いたくないということで入院せず、鍼灸で治療を希望され来院されました。
後太陽、翳風、頬車、豊隆、陽白、下関、地倉、承漿などのツボを使い、5回ほどで前額部に皺がよるようになり、兎眼や頬の麻痺もなくなり、口に空気をためても漏れなくなり、治療を終了しました。以後再発はありません。大学病院系の鍼灸治療でもこれらのツボに置鍼15分などという治療をしているようですが、これでは治療期間の短縮は望めません。ツボの組み合わせや関連する経絡にエネルギーを供給するシステムの調整などを併用すると治療期間を短縮できますが、それには古典を臨床に使用するためのノウハウが必要です。
後から考えると耳痛や耳の周囲の水疱を記録していないので、ハント症候群ではなかったかもしれないのですが、以前に何ヶ月もステロイドを使われてから顔面神経麻痺で来院された方などは、今回のようにすぐには改善しませんでした。これが第2のポイントです。
最初の方のように明確にステロイドを拒否される方は別ですが、初診時の病院で適切な東洋医学的対処があれば、患者さんの負担も軽くなるとつくづく感じた次第です。
アトピー性皮膚炎の鍼灸治療
今回の患者さんは鍼灸学校の学生さんです。ということでいろいろな鍼を試した結果報告も兼ねています(笑)
筋肉質なのですが、元々体は弱く、のぼせ、手足の冷え、下痢等があったそうです。今でも汗をかきやすかったり、体や眼の疲れ、きちんとした睡眠がとれない等があります。
更年期障害の早期回復は鍼灸治療の併用で
更年期とは、卵巣の機能が衰えて特にエストロゲン(卵巣ホルモン)が減ることで起こる種々の症状のことを言いますが、イライラ、めまい、ほてり、のぼせ、頭痛、動悸、息切れ、汗をかきやすい、不眠、情緒不安定、食欲がないといった自律神経失調症状や肩こり、腰痛、関節痛といった痛み、しびれ、めまい、残尿感などの多様な症状が起こるため何科に受診するかを悩む方も多いでしょう。
重要なことは最初から体にとってきつい治療を選択しないということです。きつい治療とはホルモンに関連するものや強い作用の抗鬱剤などで、心療内科などを選択すれば比較的マイルドな薬から処方してくれると思います。婦人科はその先生の治療方針によりますね。精神科はこの程度の症状では受診しない方が無難です。最初に受診する科が重要なんです。
以下症例で鍼灸の利点を説明します。
五十代女性で更年期障害の方。頭痛・肩凝り・動悸がして、特に頭痛と動悸がひどいということでした。そこで内関・膻中・頭維・豊隆に鍼をして、公孫・心兪に跡がつかないように灸をし、肩背部・下肢に円利鍼で散鍼をして様子をうかがうと、「頭痛は無くなっています。あれっ、動悸もしていません。」とのこと。複数の愁訴が無くなってしまったので、驚いたご様子でした。
このように鍼灸では複数の症状が一気にとれることは良くあることで、西洋医学のように一つの症状に一つの薬が処方されて、次々薬が増えていくこと自体ありません。症状が減れば薬も減る訳ですから、胃腸が弱くて薬をたくさん飲めないという人にとってはお勧めの方法です。
【打鍼治験#1】呼吸時の背中の痛み
打鍼は打鍼中興の祖である、御薗意斎の学術ブレーンであった沢庵宗彭(安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧。大徳寺住持)が『刺鍼要致』に「病、頭にあるも、また腹において刺し、脚にあるもまた腹において刺す。一身の病、すべて腹において刺す。」と残しているように、腹部への刺鍼だけで、全身の症状に対応する日本独自の鍼術です。
とはいえ、腹部への刺鍼だけで治せるとしたらどんな原理なのか?ということを追求していた時にある先生のやり方に出会い、現在その先生と共に無分流打鍼を再構成しています。詳しくはこちら。これが発表できるようになるかどうか分かりませんが、臨床例は残しておこうと思います。
症状は息を吸うと、背中が痛む。そのために呼吸が浅い。鍼灸治療はしてもらっていたが、前述の症状だけが取れないという患者さんの症例です。
痛む前の状況を訪ねてみると、胃腸の状態が悪く、初診時も胃の張りや手足の冷えは訴えておられましたので、打鍼メインでいくことにしました。恐らく胃腸の位置を調整して、胸郭のスペースを広げるという打鍼の基本的パターンであろうと思われます。
腹診をすると、腹力は左が弱く左の天枢付近に細き筋があります。上部は肺先付近に強みがあるので、火曳きの鍼、負け曳きの鍼をした後、勝ち曳きの鍼で強みを調整しました。この時の刺激量は、槌の音と『針治書』の迎随の記載を参考にその場で決定していきます。
終了後尋ねると、「呼吸が楽にできるようになりました。背中も痛くないです。どうしても残って取れなかったのですけど。」ということでした。
書痙の鍼灸治療
今回の患者さんは書痙(しょけい)を訴えて来院されました。
書痙とは、字を書こうとする時、または字を書いている最中に、手が振え、または痛みが発生し、字を書くことが困難となる書字障害つまり、動作特異性で、上肢の局所性ジストニアです。
症状は字を書こうとするときに手が振え、細い字を書こうとするとペンが止まってしまい力が入らないようで、もう一方の手で支えなければ字が書けなくなる状況で、手(特に大腸経)や肩の凝りはかなりありました。
この方は緊張しやすい性格とは思いますが、特に大勢の人前で書く職業でもなく、病院に行くより先に来院されたので、小脳などを対象にした西洋医学的検査や診断はうけておりません。
治療
全身の状態は心包・三焦システム、特に中焦の異常で、大腸経と頸肩の凝りが顕著にありました。そこで心包・三焦システムの調整と中睆に鍼をして、大腸経は董氏の倒馬鍼方、頸肩は皮膚刺絡をした後に上肢全体の筋・腱を調整しました。
この後、字を書いてもらうと「あっ書けるようになりました。」とすらすらと書いていました。念のため小さい字も書いてもらいましたが、問題なく書けているようでした。その後も再発したという連絡はありません。
ジストニアに関して鍼灸治療が有効であるという報告がありますが、私はまず鍼灸を選択してみるべきと思います。
他の疾患でも書いていますが、一般的には人前で書く時に振える場合、神経内科などが担当科となり、消炎鎮痛剤ではない抗うつ剤系の薬物療法が最初から選択されることが多いです。この手の薬を飲んでから来院される方は本当に治りが悪いので困りますね。
神経症の治療には半年以上の長い期間が必要なので、何ヶ月も服用してから鍼を選ぶのであれば、最初から鍼を選んでもらえば、この患者さんのように治療期間は短くて済むという訳です。ぜひご検討ください。
【症例2】
4〜5年前から字を書く時に手が震えるようになった。ホワイトボードは平気だが人が見ている前で書こうとすると、特にひどくなるという訴えでした。
パニック障害の治療によく使われる、ベンゾジアゼピン系抗不安薬のランドセン(リボトリール)を処方されているけれども変化がないので、鍼灸を試してみたいとのこと。
この方も全身の状態は心包・三焦システム、初回は上焦、その後中焦の異常で、打鍼で中焦のブロックを除去し、肺経、大腸経、三焦経の筋・腱を調整しました。さらに董氏の重子、重仙、中白、下白などのツボを使いました。
3回目で見られていなければ滑らかに書けるようになってきて、4回目で腕全体に力を入れず指だけで書けるようになったということで、治療を終了しました。ご参考までに字のサンプルを載せておきます。
やはり薬を飲まれている方の場合は、治療期間が伸びてしまうようです。
全頭脱毛の鍼灸治療
今回は最初に来院されたときの状態が、頭髪は全くない状態だった症例についてお話します。
2人とも頭部の皮膚も触ってみるとつるつるしていて、毛根も全く見当たらない状態でした。また、また頭だけでなく眉毛や体の他の部分にも毛がない状態でした。
伝統医学では、元々体のパーツと臓器の関係が設定されていて、古代中国医学の論文集である『素問』の六節臓象論篇には「腎の華は髪にあり」という記載があります。これは腎の持っているエネルギーの盛衰と頭髪の成長・脱落が関係していることを示唆しています。
伝統医学ではこのような考えをもとにどのように治療するかを決定していきます。また、「髪は血の余となす」ともいうため、蔵血機能を有している肝も同時に治療することにしました。
肝腎要というように元々肝と腎は密接な関係にあり、治療上でも肝と腎を整えて行くことは意味のあることなのです。
Aさんは2年前から円形脱毛が始まり、8ヶ月前より全脱毛になってしまったという経過です。そこで今回は肝兪、命門というツボにお灸をして、肝・腎のエネルギーを高めることにしました。
これだけでは少し足りないので、首・肩の凝りをとって頭部の循環を良くし、頭部と眉毛の部分を鑱鍼(ざんしん)で刺激することにしました。さらに肝兪、志室は自宅でお灸をしてもらうようにし、頭頂部の百会というツボにもお灸をしました。
鑱鍼というのは九鍼と呼ばれる昔から伝わる九種類の鍼の一つで、普通の鍼と違い刺さずに皮膚を擦るように使います。Aさんは2回目で髭と眉毛が出始め、体の冷えがとれてきたということで4回目には1mm程度の頭髪が全体に広がってきました。1mm程度になるとあとはどんどん戻ってきます。
Bさんは幼いときからアトピーがあり、2005年に悪化して漢方や鍼をしていましたが2008年に全頭脱毛になってしまったという経過の患者さんです。
この方は肝兪、命門の力が非常に弱く、治療開始から7回目まではあまり変化がありませんでした。そこで8回目から頭部の刺絡を加えたところ、9回目で初めて眉毛が生えてきてしばらくそのままの状態が続いていましたが、17回目で眉毛の部分が広がって右の頭頂部にも発毛がみられ、18回目で顔に産毛が出始め、1mm程度の頭髪も全体に広がってきました。部分的に残った場合は、その部分にだけ刺絡+知熱灸+鑱鍼という形で脱毛部の範囲を狭めます。
AさんもBさんも出始めたのは眉毛からというのが印象的でした。Aさんの場合は鑱鍼で刺激していると、頭部全体がすぐに発赤してくるので反応がいいなと感じましたし、数回の治療で発毛してきたのもそのせいかと思われます。
むちうち症の鍼灸治療
伝統医学では人間の体に十二本の経絡があって、そこに流れている気が循環していれば、病気にならないと古の人たちは考えていました。しかし様々な原因でその流れが堰き止められてしまうと、溝の中の泥のように止めているものを排除する必要が出てきます。
そこで目的別に最も効果的にいらないものを排除して、流れを回復するための道具を考え出しました。それが鍼灸の最も古い古典である『黄帝内経』に書かれている九鍼です。
九鍼はその後中国でも全てを使うことは稀になり、日本でも江戸時代には三種類くらいあれば十分と書かれるようになり、形や使用法も曖昧になってきてしまいました。近年の韓国ドラマでも間違った使われ方がされていて、笑ってしまいましたが。
私も所属している東京九鍼研究会は、これらの鍼を歴史の中から掘り起こして、臨床に使っているグループなのですが、以下にその代表的な症例を上げてみたいと思います。
2ヶ月前にタクシーと接触事故によってむちうち症と診断され、整形外科や整体に通っていたが、深部が残っていて頸は左右の可動域に制限があり、下を向くと痛む。それに伴い後頭部に頭痛がするという患者さんでした。この方は敏感な体質の方だったので、2回ほどは奇経の調整などで様子を見ていました。
毎回施述が終わる時には愁訴は無くなっていて、当初あった背中の痛みも無くなったのですが、頸の可動域減少と頭痛が時々あるということでした。そこで肩に鋒鍼(三稜鍼)で刺絡を加えたところ、三回で全ての愁訴がなくなりました。
この方ような敏感な方でも局所的にいらないものを排除する場合は、普通の鍼(毫鍼)よりも刺激の強い方法でもなんら問題ありませんし、相手に許容量以上の刺激を与えて、体調を悪くしてしまうこともありません。『黄帝内経』に書かれている「鋒鍼(三稜鍼)で刺絡が手技の補瀉を超越した概念だ」ということは、そのような意味なのです。
鍼灸の解熱法(試用版七星鍼法)
詳しい方法は著作権があるので書きませんが、ぜひ『人体惑星試論奥義書』で確かめてみて下さい。つまらない講習会に何十万も使うなら、この本は激安だと思います。